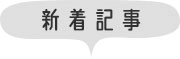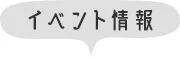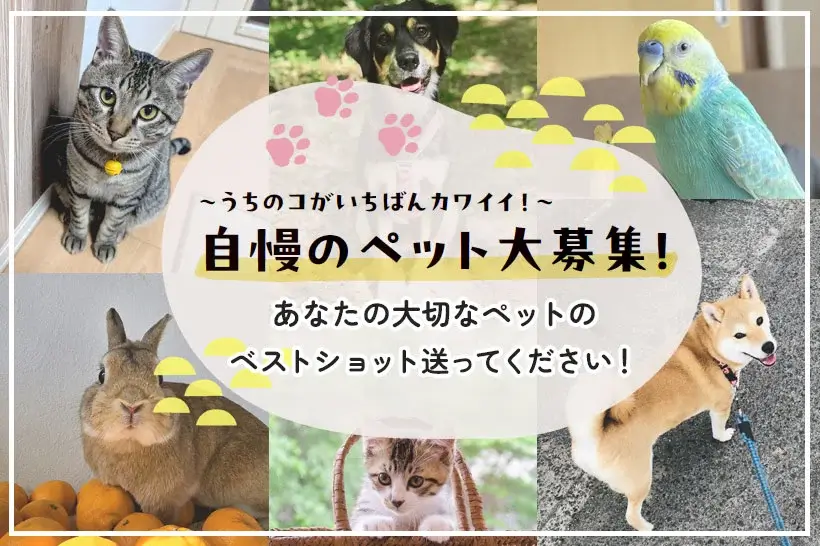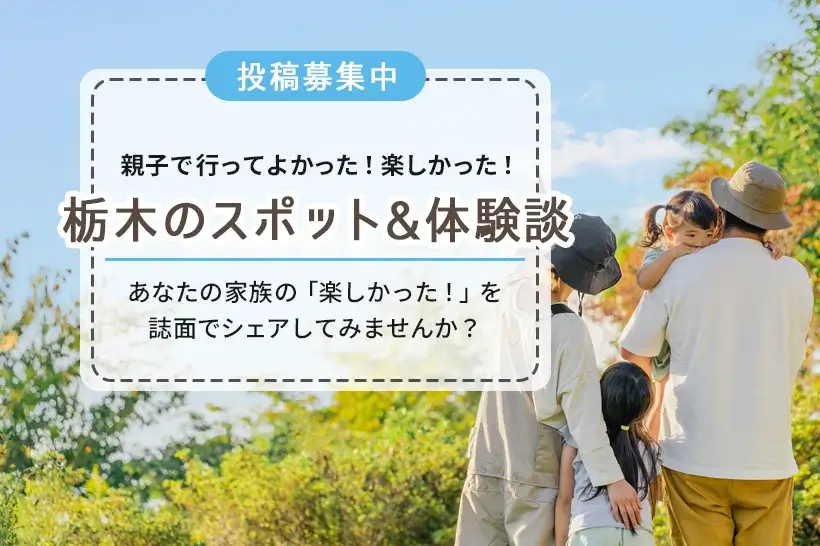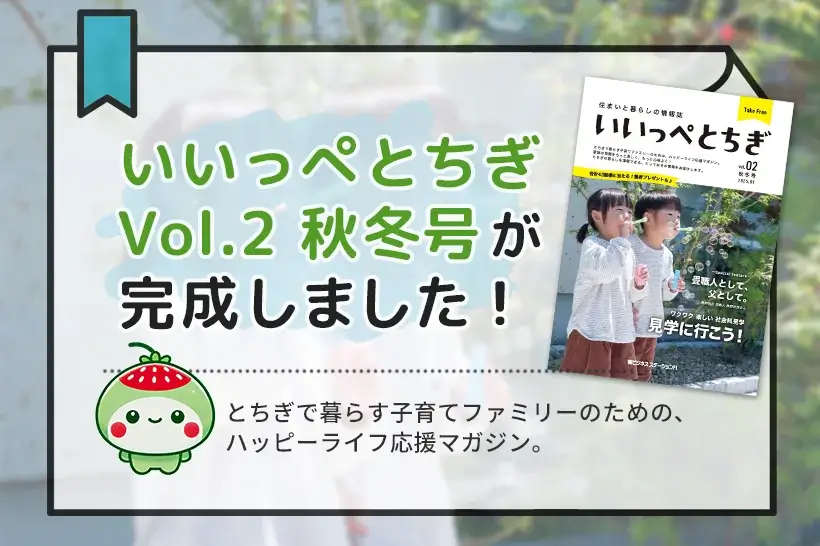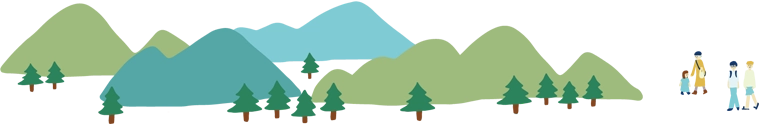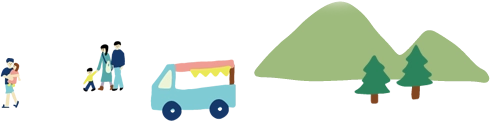子どもから大人へ、十三歳の祈り
十三参りとは、数え年13歳になった男女が虚空蔵菩薩にお参りする習俗である。なかでも京都嵐山の法輪寺(通称、嵯峨の虚空蔵さん)への十三参りはよく知られ、4月13日(旧暦3月13日)の祭日には多くの参詣者で賑わう。虚空蔵様は無限の智恵と慈悲をそなえた菩薩で、そこで売っている13種類の菓子をお供えし、家に持ち帰って食べると厄難から免れ、福徳と知恵が授かるといわれる。
十三参りは、七五三などと比べると一般的ではないが、栃木県では那須郡や芳賀郡など八溝山麓の地域で行われていた。このうち那須町など県の北部では福島県柳津町にある霊巌山円蔵寺(柳津虚空蔵・福満虚空蔵)、芳賀郡では茨城県東海村の村松虚空蔵尊(村松山の虚空蔵さん)に参詣した。その際に4月13日ではなく、正月や春休み、あるいは夏に海水浴を兼ねて出かける人も多く、たいがいは父親が連れて行くが、近所に住む子供たちを集めて集団で、あるいは小学校で参加者を募って出かけることもあった。

舟で、汽車で──十三参りは旅のはじまり
かつて、那珂川流域では舟で十三参りに行った。明治30(1897)年に現在の那須烏山市向田に生まれた人によれば、「数え13歳の時、那珂川の堤防より便乗した。同じ所から6人乗り合わせて20人ほどになった。舟は馬舟よりも胴が細く長かった。舟底には荷物が積んであり、その上に板を載せ、さらにゴザを敷いて、その上に座った。朝8時に出発し、水戸の下市に着いたのが午後4時であった。その日はここに泊まり、翌日蒸気船で関門橋まで行き、そこから歩いて村松虚空蔵さんへ行ってお参りをすませ、平磯に宿泊した。

次の日は汽車で笠間まで行って宿泊し、翌日歩いて帰ってきた」(『烏山町史』より)。大正時代になって真岡線(現真岡鐵道)が開通すると、真岡や益子の子供たちは、鉄道を使って十三参りに出かけるようになった。現在も自家用車や貸し切りバスで行く人もいる。

成長の節目として、そして楽しい記憶として
13歳とは、生まれた時の干支が一回りした年齢、元服もこの年齢の前後に行われていた。つまり、子どもから大人への節目として意識されていた。それ以上に、旅行などにあまり連れて行ってもらえなかった当時の子どもたちにとって、十三参りとは舟や汽車に乗ったり、海で遊んだりすることができる数少ない機会でもあった。そのため、楽しい思い出として記憶に残っている人は多い。
1965年、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮大学大学院教育学研究科社会科教育専修修了。栃木県立足利商業高等学校、同喜連川高等学校の教諭を経て、1999年より栃木県立博物館勤務。民俗研究、とくに生活文化や祭り、芸能等を専門とし、企画展を担当。著書に『栃木民俗探訪』(下野新聞社)などがある。