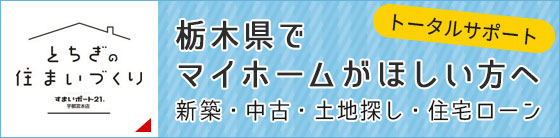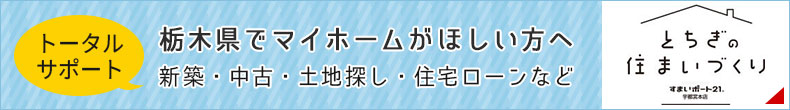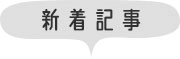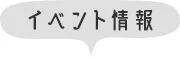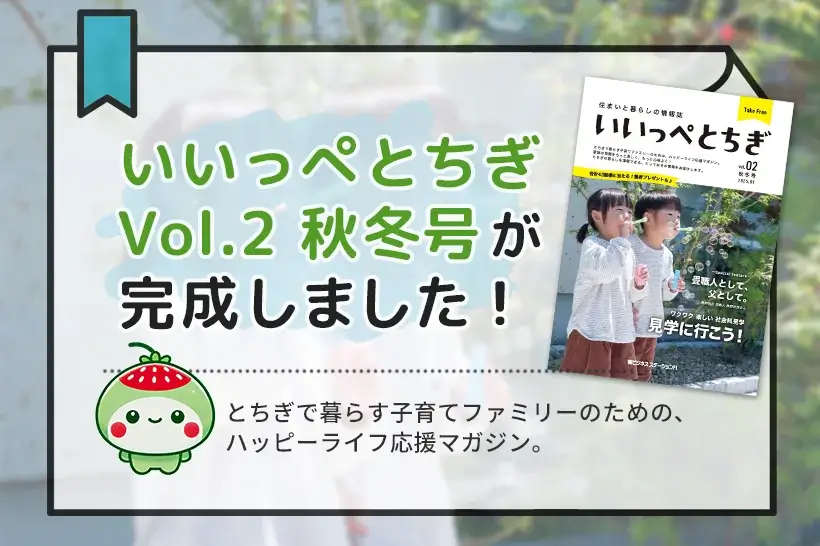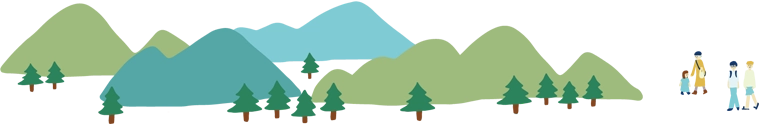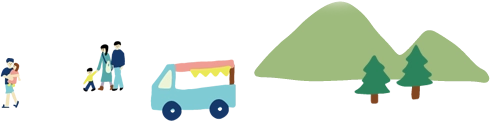米俵を担げば大人? 一人前の「重さ」と「量」
成人の基準に達した状態のことを一人前とか一丁前(いっちょまえ)という。多くは仕事量で測られ、男子であれば一俵(60㎏)の米俵を担いで歩けること、あるいは鋤で一日に3畝(約20アール)の畑を起こすことができると一人前いわれた。
一方、女子は機織りができることや一日に8畝(約53アール)の田植えができることが基準とされた。このような基準は時代によって変化し、また各地で地域特有の基準も見られた。例えば、麻の生産農家に生まれた鹿沼市の女子は、一日に1貫目(3.75㎏)の麻をひくことが求められた。これらは、労働の対価として支払われる賃金にも反映されるので重要であった。
力石に試される若者たち──神社に残る挑戦の痕跡
力の強さが一人前の基準とされることもある。「力石」などと呼ばれる大きな石を持ち上げることができて一人前とする事例は各地に見られ、栃木市の大神神社(惣社町)や八幡宮(都賀町)などの境内には、現在も「力石」が祀られている。こうした力石は、人生儀礼としてのセレモニーの他、若者たちによる力くらべの娯楽にも使用されていた。
地域が育てた“おとな”──若者組と娘組という制度
これ以外の基準としては、男子は集落ごとに作られた「若者組」に入会する数え年15歳が一人前の目安とされた。一般に若者組とは、結婚前の青年男子で構成された組織で、その構成員であるワカイシ(若い衆)、ワカシュウ(若衆)は、若者として守るべき厳格な規約のもと、地域の自警や消防にあたった。また祭りの運営において、重要な役割を任された。一方、女子は女性の生理的な変化、すなわち月のものが来ると「娘組」に入り、先輩や同齢の女性などから炊事や裁縫などを学ぶことで女子力を磨いた。
一人前になると、男子であれば大人と対等な立場となり、満額の手当がもらえるようになる。一方、女子は周囲から嫁入りできる年齢になったと認識される。若者組や娘組の多くは昭和初期頃までには消滅し、青年会や青年団、女子青年団と呼ばれていた女性の団体などに再編されていく。しかし、少子高齢化や過疎化に加え、加入にあたり強制力がなくなったことで、地域の若者が集い、活躍できる場は少なくなっている。とはいえ、地域の結束力を高め、良きにつけ悪しきにつけ先輩諸兄から一人前の人間となるための素養を学ぶ場であったことは事実である。そう考えると若者組や娘組の衰退が、地域の活力の低下の一因になっているのかも知れない。
1965年、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮大学大学院教育学研究科社会科教育専修修了。栃木県立足利商業高等学校、同喜連川高等学校の教諭を経て、1999年より栃木県立博物館勤務。民俗研究、とくに生活文化や祭り、芸能等を専門とし、企画展を担当。著書に『栃木民俗探訪』(下野新聞社)などがある。