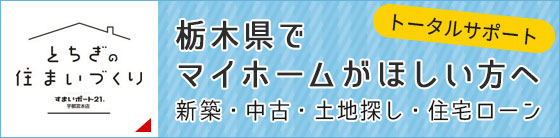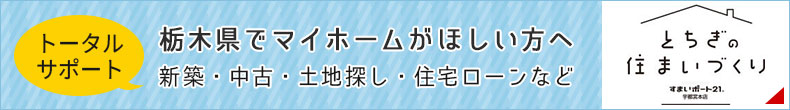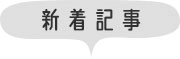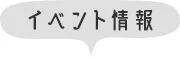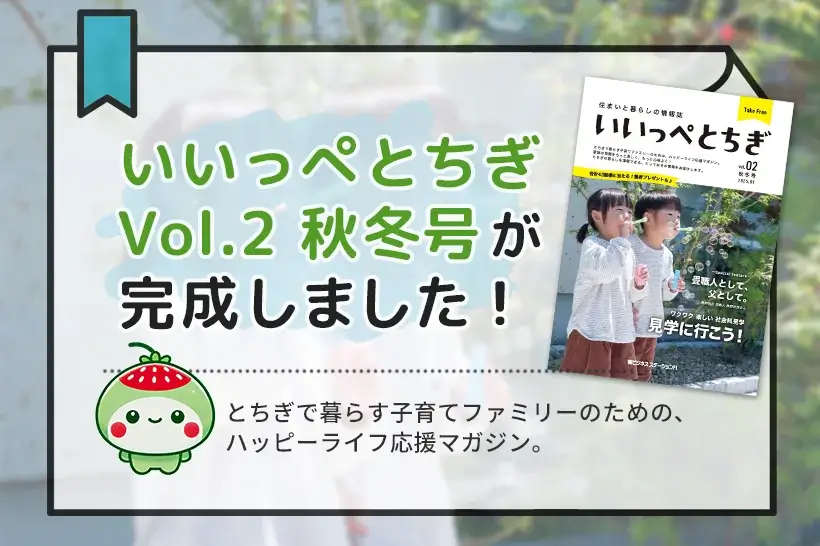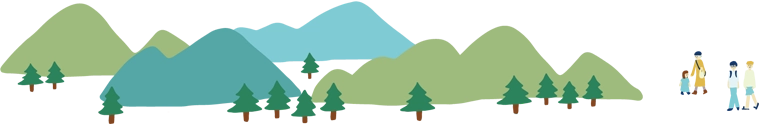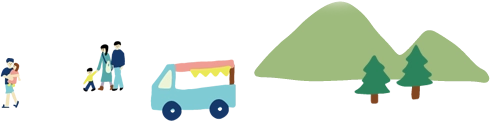神に認められる「宮参り」―赤子の社会的な第一歩
赤ん坊が生後初めて神社(氏神様)に参る儀礼を宮参りという。早いところではお七夜にあわせて、遅くとも生後100日目までに、多くは生後30日前後に行うが、男児は32日目、女児は33日目というように男児か女児かで違う日に行う場合もある(女児を先とする地域もある)。宮参りは赤ん坊の無事成長を願う儀礼で、これをもって、その存在が神様に認められた。かつては、産婆や仲人、姑などが赤ん坊を抱いて神社に詣でたが、現在は母親も同行することが多い。
「お食い初め」と「歯固め」―健やかな成長を願う食の儀式
生後100日目頃になるとお食い初めを行う。この日は、赤ん坊のために膳と椀を用意し、尾頭付きの鯛や煮物、紅白なます、吸い物などを盛り付けた。そして、招待された里親や産婆、仲人などが、料理を箸でつまんで赤ん坊の口元に運んだ。あわせて、氏神様などからいただいた石を膳に載せる。この石は「歯固めの石」などと呼ばれ、同じく赤ん坊の口元に運んで食べさせる真似をした。あるいはなめさせた。これには「歯が丈夫になるように」という願いが込められている。芳賀町や高根沢町などでは、使い終わった箸に水引をかけて、氏神様の拝殿の扉にくくりつけた。
一升餅から初正月まで―節目ごとに込められた未来への祈り
生後一年目の赤ん坊の誕生日には、一升の餅を搗いて風呂敷に包み、赤ん坊に背負わせた。この時、上手に歩けたらわざと転ばせたという。地域によっては、赤ん坊の目の前に物差しや筆、算盤などを置き、何を手にしたかで、その子の将来を占った。

出生後、初めて迎える正月を初正月という。赤ん坊にとっては初めての年取りの日である(年が1つ増える日のこと。戦前は大晦日(もしくは節分)をもって年が1つ増えるとされた。生まれた時が1歳、次の正月がきて2歳と数える。こうした年の数え方を満年齢に対して数え年という。初誕生を例外とすれば毎年の誕生日を祝うことはなかった)。この日にあわせて、嫁の実家では、男児なら破魔弓、女児なら羽子板や毬などを贈った。また、初めて迎える節供には、同じく男児であれば鯉幟や武者幟、武者人形、女児であれば雛人形を贈った。当家では祝いの膳を用意し、親戚や近所の人たちに菱餅や柏餅を配った。特に長男長女の場合には盛大に行った。
宮参り、お食い初め、初正月など、成長の節目に行う儀礼は、子の無事成長を神仏に感謝し、加護を求めるものである。あわせて家族の祝いとお披露目の意味もあった。儀礼の内容は変化しているが、子どもにかける想いは、現在も昔と変わらない。
※掲載写真はすべて栃木県立博物館提供
1965年、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮大学大学院教育学研究科社会科教育専修修了。栃木県立足利商業高等学校、同喜連川高等学校の教諭を経て、1999年より栃木県立博物館勤務。民俗研究、とくに生活文化や祭り、芸能等を専門とし、企画展を担当。著書に『栃木民俗探訪』(下野新聞社)などがある。