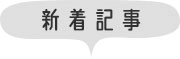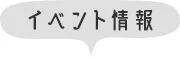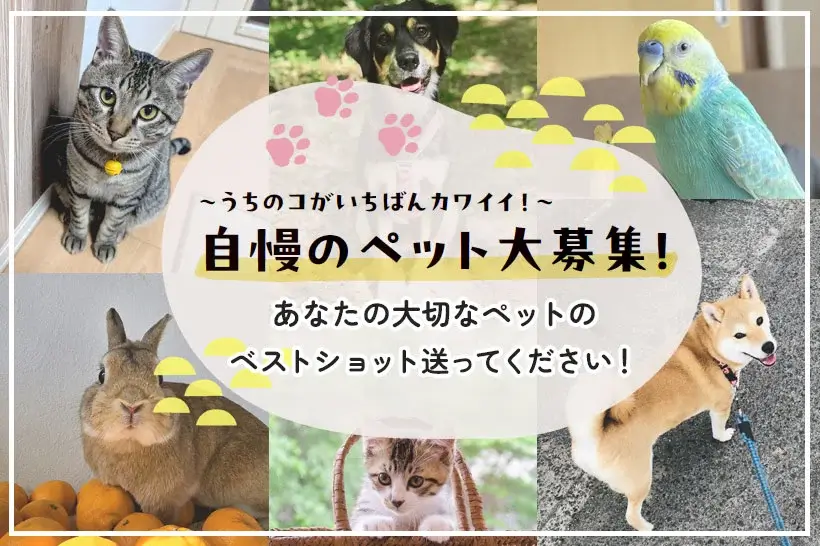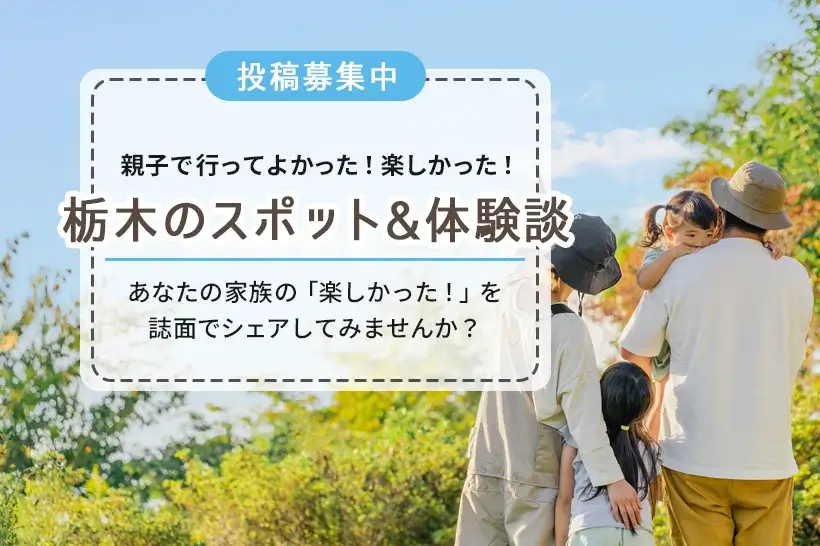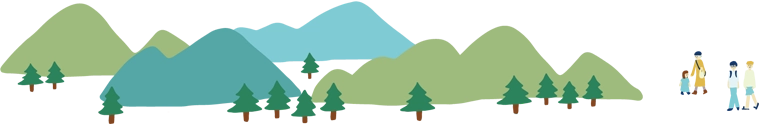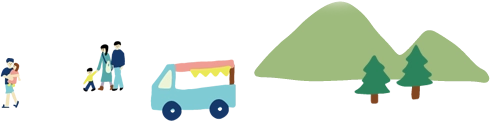華やかな式場やホテルで行われる結婚式が当たり前になった今。しかし栃木では、昭和30年代頃まで、結婚式は家で営まれるのが一般的でした。地域ごとに異なるしきたり、家々が協力し合う祝言の準備、そしてどこかあたたかい嫁入りの風景。今回は、当時の結婚式の姿を紹介します。
家からはじまる、昔のハレの日
かつて、結婚式はゴシュウギ(御祝儀)と呼ばれた。今も昔も人生における最大のハレの日の一つである。今日、結婚式は式場やホテル、神社、教会などで行われることが多くなったが、昭和30年代以前は家で挙げていた。ここでは、当時の結婚式の様子を紹介する。
結婚式の当日、新郎は、朝一番に紋付き羽織袴で身を整え、仲人やおじ、おばなどとともに新婦の家に向かう。到着すると、奥座敷に通され、新婦の両親や親戚と挨拶を交わした後、新婦方のおじやおばに連れられて近所回りに出かけた。
一方、新婦は早朝から髪結い、着付けに忙しい。準備が整ったら仲人やおじ、おば、髪結いなどとともに人力車や車などで新郎の家に向かった。大正時代以前は飾り立てた馬で、シャンシャンと音をたてながら嫁入りしたという。

嫁入り行列に宿る“祈り”と“境界を越える儀式”
新婦が婚家に入るのは夕方になってからである。その際に宇都宮近辺ではそれぞれの家の家紋の入った提灯を互いに3回取り交すチョウチントッケ(提灯取り替え)を行った。また、鹿沼では麻殻の松明の火の上をまたいでから家に入った。これらは神聖な麻や火で身を清めるためといわれている。
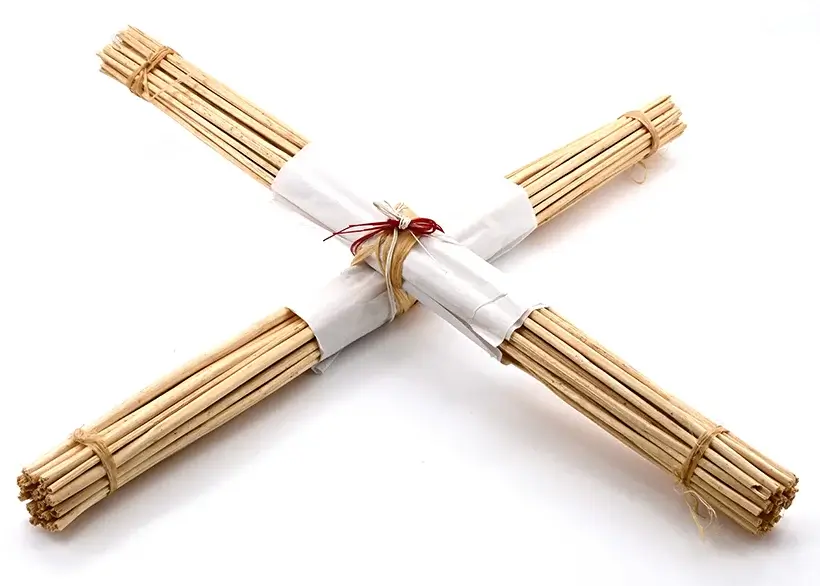
その他にも、家に入ろうとする時に花嫁の頭上に笠を被せるカサカブセ(笠被せ)、花嫁の尻を箒などで叩くシリタタキ(尻叩き)などを行う地域もあった。嫁入りとは、他人の血を当家に入れることであるが、そのための呪術的な儀式と考えられている。

家に入ると座敷に通され、まず桜茶(桜湯)を飲み、おちつき餅を食べた。そして、一段落したら三三九度の儀式となる。仏壇のある部屋などに新郎と新婦が並んで座り、雄蝶、雌蝶と呼ぶ小学校にあがるかあがらないかぐらいの男の子と女の子に大・中・小の3つの盃に酌をしてもらう。いわゆる夫婦固めの盃で、この三つの盃で3回ずつ酒を酌み交わすことで夫婦の契りを結ぶ。その後、オショウバンニン(お相伴人)と呼ぶ特につきあいの深い人の仲立ちで、家族や親類との引き合わせを行う。
三日続く祝宴、地域がひとつになる時間
その間、別室では宴会が進められている。いわゆる披露宴である。親戚や組内、恩師、友人などを招いて、近所の魚屋や仕出し屋が用意した刺身、酢の物、煮魚、煮物、蒲鉾など5品、もしくは7品の料理で振る舞った。また引き出物として羊羹、鶴亀をかたどった菓子、口取り(きんとんや蒲鉾)、お頭付きの鯛なども用意した。

三三九度の儀式が終わると新郎と新婦も同席し、招待者に酒をついで回った。祝宴は、3日間にわたって続くこともあった。
1965年、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮大学大学院教育学研究科社会科教育専修修了。栃木県立足利商業高等学校、同喜連川高等学校の教諭を経て、1999年より栃木県立博物館勤務。民俗研究、とくに生活文化や祭り、芸能等を専門とし、企画展を担当。著書に『栃木民俗探訪』(下野新聞社)などがある。