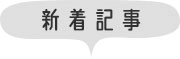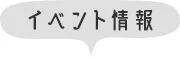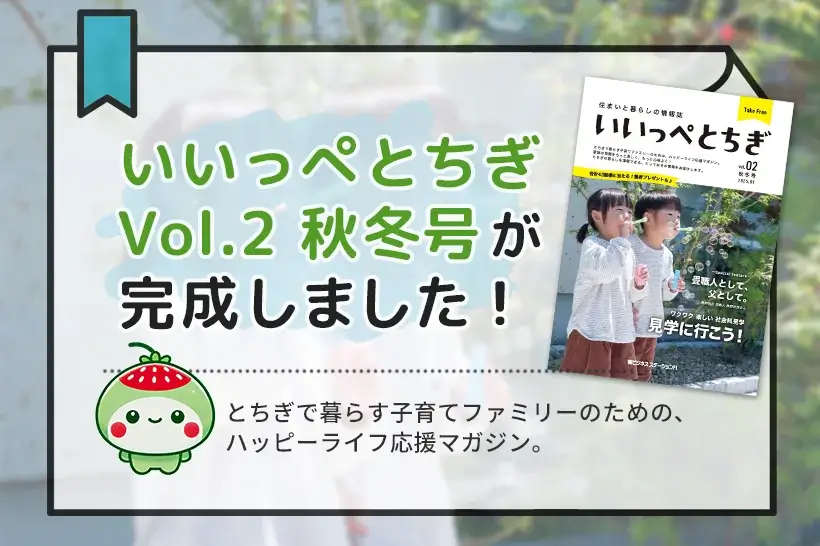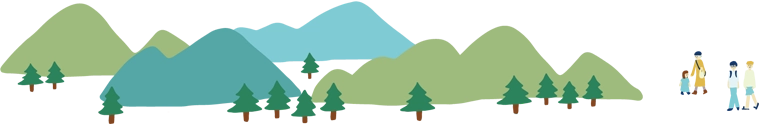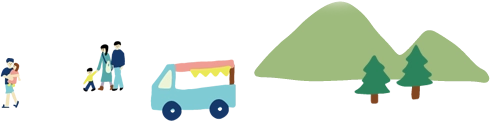良縁を願う祈りと占い
結婚は、人生のなかで最も重要な通過儀礼の一つである。一昔前までは「結婚して一人前」といわれ、独身のままでいるとプレッシャーをかけられることもあった。そのため良縁を夢見て縁結びの神様にすがったり、手相、人相、星座、タロットなどの相性占いに一喜一憂したりしたが、これらは現在につながる習俗である。
見合いと「家」の思惑
かつては見合いによる結婚が多く、見合いの席で女性が出したお茶を男性が飲んだら承諾の合図とされた。また、両親の顔を立ててしぶしぶ見合いの席に臨んだとか、見合いの時ははずかしくて相手の顔を見ることができず結婚式当日にはじめて相手の顔を見たなどのエピソードは、あちらこちらで聞くことができる。そうしたなか、恋愛で結ばれたおじいちゃんやおばあちゃんのなれ初めを聞くと、なんて先進的なのかと感心したりもする。
ただし、これらは明治時代から戦前あたりに広まった倫理観で、それ以前の若者は自由な恋愛を楽しんでいたようだ。個人差もあるだろうが、男女の駆け引きは現代の私たちより激しく、上手だったかも知れない。そして離婚率や再婚率は現在よりも高かった。
しかし、庶民に経済力の格差が広がり、家と家との釣り合いが重視されると、同程度の身分や経済力の家から結婚の相手を求めるようになった。もちろん「身分をこえた愛」も普通に見られたが、決して歓迎されるものではなかった。そのため「家」か「愛」のどちらをとるかに悩み、駆け落ちや心中に至ることもあった。その一方で、結婚は家の格を上げるチャンスでもあった。「玉の輿」や「政略結婚」がよい例である。
仲人からマッチングアプリへ
そうしたなか、「家と家との橋渡し」つまり、結婚適齢期の男女を結び付けたのが仲人である。仲人は地域に顔が利く人や世話好きな人、あるいは上司や恩師などがなり、両親などの求めに応じて、同じような家格の家から適当な相手を探してくる。こうして、本人の知らないところで、お見合いの話が進められた。
戦後になると、恋愛結婚が主流となり、事実婚や同性婚など結婚に関する価値観は大きく変化した。また生涯独身を選択する人も増えている。それに伴って、仲人が活躍する場面は少なくなり、仲人そのものを嫌う風潮さえ生まれた。代わって登場するのが結婚相談所やマッチングアプリであるが、容姿や年齢、年収、趣味などをもとにして相手を探し、出会いの場を設定している点では、仲人やお見合いとさほど変わりはない。
1965年、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮大学大学院教育学研究科社会科教育専修修了。栃木県立足利商業高等学校、同喜連川高等学校の教諭を経て、1999年より栃木県立博物館勤務。民俗研究、とくに生活文化や祭り、芸能等を専門とし、企画展を担当。著書に『栃木民俗探訪』(下野新聞社)などがある。