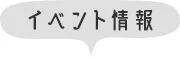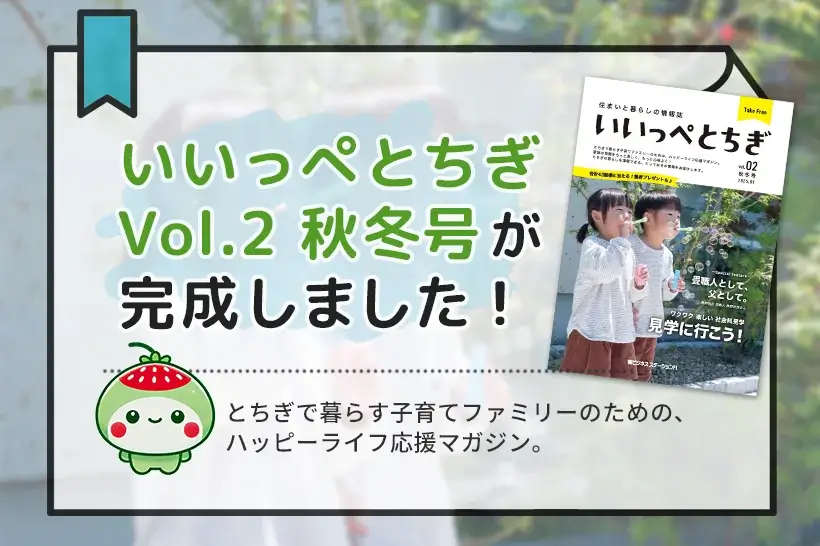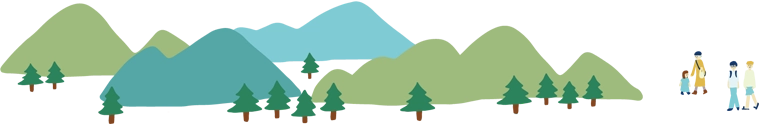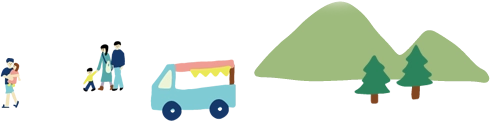宇都宮市在住のアーティスト。デザインやイラスト制作を手掛ける傍ら、ペインターとしてイベントなどでのワークショップも開催。台湾に事務所をもち、海外活動にも力をいれている。展示会などの情報はHPを。
https://www.instagram.com/michico_motoki
点と線で描かれる独創的な世界
一本のペンを片手に、大型ウインドウの前に立つアーティスト・もときみちこさん。デザイナーとして仕事をする傍ら、美容院やカフェなどのショーウインドウや壁面に絵を描く、ミューラル・ウィンドウペインターとしても活躍しています。
個性派ぞろいのキャラクターや架空の植物……。点と線で描かれた独創的な世界観は、一見シンプルなのに、見入ると喜怒哀楽が複雑に入り混じる、奥めいた魅力をもっています。
「自分に何ができる?」そんな問いかけを胸に、もときさんは今日も、目の前の大きなキャンバスに、その答えとなる“ありのままの自分”を描いています。

自然の中で遊び、絵を描くのが大好きだった
もときさんが生まれ育ったのは、高根沢町の自然豊かな田園地帯。幼い頃は、住まいのすぐ側にある山に入り、よく自然遊びを楽しんでいたそうです。その一方で、絵を描くのも大好きで、小学校に上がると「大人になったら漫画家になりたい」と、漠然と思うように。それでも特別なことはせず、好きな時に好きな絵を描く、そんな日々を送っていたといいます。

挫折の先に見えた本当に好きなこと
中学生になるとバレーボールに夢中になったもときさんは、悩んだ末に美術科のある高校ではなく、バレーボールの強豪校に進学を決意。しかし、想像以上に部活動が厳しく、もときさんはバレーボールの道を断念してしまいます。
「好きで入ったのに、続けられない自分に不甲斐なさを感じていました。でも、この挫折がきっかけで、この先、自分には何ができるんだろうって、自分自身を見つめなおすことができたんです。それが絵だった。ずっと好きで続けてこられた、絵を描くことだったんです」

自分の声を表現する難しさ
「絵しかなかった」。それが、もときさんが生まれて初めての挫折から見い出した。新たな次の道標でした。高校卒業後、もときさんは短大でデザインを専攻。ようやく腰を据えて美術の世界へ……というはずが、現実はというと、友人と遊び、バイトに明け暮れる毎日だったとか。
「短大生になったら、遊ぶことがとにかく楽しくなってしまったんです。当時を振り返っても、自分は何と向き合い何を学んだんだろうという、2年間を過ごしてしまいました。そして『好きなだけじゃダメなんだ』ということを、痛感した2年間でもありました」
考えのない絵はダメ?
好きだから描く、描きたいから描くといった、これまでのスタイルが、世間では通用しないことを思い知らされた、もときさん。それは、短大時代のある教授の一言がきっかけでした。「お互いの作品を批評し合う授業のなかで、私の絵を見て教授がこう言ったんです。『僕にはない感性だ。基本がなってないからね。最低だ』と。もう、唖然としましたよ。実際、教授のおっしゃる通りでしたから。これまで『これはどんな意味ですか』と聞かれても『好きだから描いただけです』としか言えない自分を、教授は『そんな考えのない絵を君は描けるんだね』って、バッサリ(笑)」
想定外のダメージを受けたもときさんは、次第に腹立たしい気持ちでいっぱいに。と同時に「そうなんだ!」という、大きな気づきを得られた瞬間だったといいます。「人に見てもらいたいなら、そこに意識を向けるべきということを、教授が気づかせてくれたんです。これは今になって思い返してみても、やっぱりあの言葉は私に『よし、やってやろう!』って奮起させてくれる一言でしたね」


絵描きの自分にできること
自己満足でしかなかった表現者としての自分を、粉々に打ち砕いてくれた一人の教授の存在。その後、ズタズタになりながらも「好き」だけでは、絵を描き続けてはこられなかった、自分の心を探し求めるように、創作に向き合うように。しかし、短大卒業後、地元のデザイン会社に就職したもときさんは、作業上で上司に意見を求められるたびに、自分の言葉で制作意図や思いを伝えることが怖くなっていったと話します。
「自分に自信がなかったんでしょうね。実績もないですし、これを言ってしまったら笑われるんじゃないか、こんな答えは求められていないんじゃないかとか。そんなことばかり、頭をよぎって、自分の言葉を失ってしまったんです」
当時は多忙な毎日で、明け方まで働いて、仮眠しに自宅に戻り、朝9時に出社するという、今では考えられないハードな会社勤め。それでも、絵を描くことはやめずに、デザイナーとして働きながら、合間を縫っては、制作した絵をコンクールに応募する日々。受賞には至りませんでしたが、表現することはあきらめません。やがて結婚を機にフリーランスへと転身したもときさんは、再び、こう思うのです。「自分に何ができるだろう?」と。
自分にしかできないこと、自分にしか描けないものを見つけたいと、試行錯誤する日々。そうして、たどり着いたのが、点と線をつなげた独創的なイラストレーション。ユーモラスでありながら、どこかシニカル。
とびきりの笑顔のなかに潜む、隠れたメッセージ。もときさんは、言葉を失った自身の“声”を、無意識のうちにイラストレーションによって、表現しているかのようでした。

道は自分で開拓していく
デザインの仕事をしながら、アーティストとしての活動の場を少しずつ広げていったもときさん。コロナ禍によって仕事や活動が減少した際も、前向きに考えることができたのは、どんなときも絵を描き続けてきたという、遠回りの人生から手に入れることができた“唯一の自信”に、気づいたからでした。
「この歳になったからこそ、わかったことがあるんです。表現の自由をせばめていたのは、自分自身なんじゃないかって。昔は何か描いていれば、そのうち、どこかの誰かが私を持ち上げてくれるだろうという、おごりを持っていた時期がありました。でも、そんなことは絶対ありえない話で、道は自分で開拓していかないといけない。自分だけができることって、自分を信じ、思いを発信することなんですよね」
自信のなさからか、自分は小さな絵を描くことや作品づくりが得意なんだと決めつけて、これまで大きなサイズの作品づくりを避けていたもときさんでしたが、多くの人にみてもらいたいという思いや、創作活動を応援する協力者の後押しもあり、やがて壁画に挑戦する機会に巡り合います。これが、初の大型ウインドウペインティングの制作となったのでした。
描くのが楽しい!
創作は一人ですが、キャンバスからウィンドウ、シールまで、さまざまなものに描き、時に陶芸家や珈琲焙煎士など他業種の人とコラボレーションして、オリジナルグッズの制作や、展示会の開催もするもときさん。自分への投げかけが、作品になり答えとなる。幾度もの挫折、そして新たな創作スタイルが、結果として自分の本質を知ることにつながり、今の私をつくってくれると、もときさんは自分を受け入れるようになれたといいます。