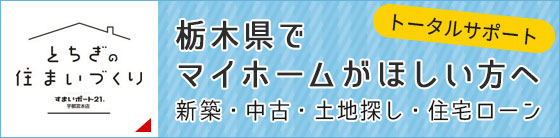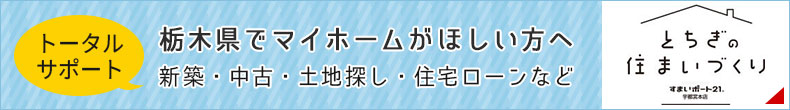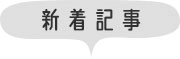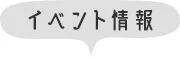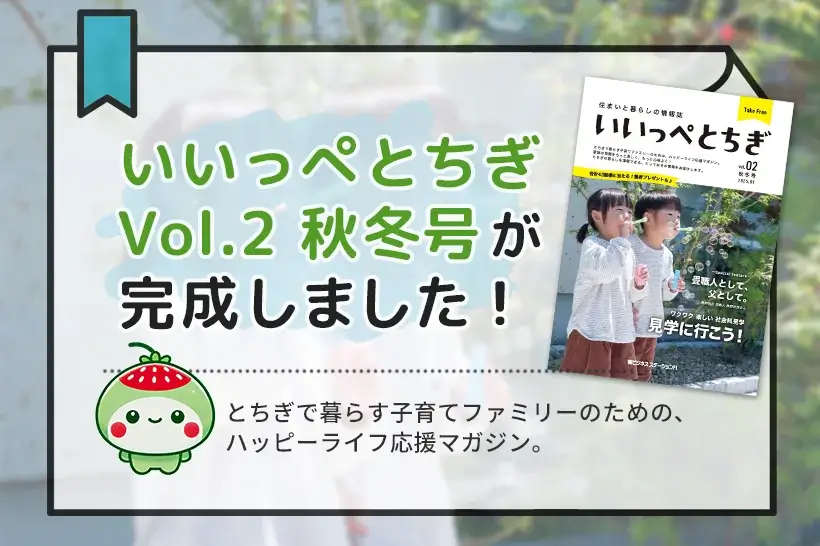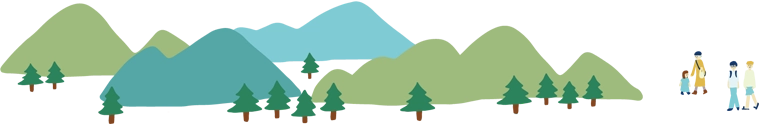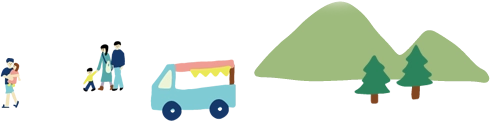今宮神社祭のはじまり
栃木県には、ユネスコ無形文化遺産に登録された祭礼行事が二つある。一つは「烏山の山あげ行事」(那須烏山市)。そしてもう一つが今回紹介する「鹿沼今宮神社祭(かぬまいまみやじんじゃさい)の屋台行事」(鹿沼市)である。いずれも山・鉾・屋台が巡行することで知られている。
鹿沼今宮神社祭の屋台行事は、今宮神社の秋の例大祭の付け祭りとして行われる。延暦元(782)年の創立とされる今宮神社は、鹿沼市内の中心部34か町の氏神として祀られ、人々の信仰を集めてきた。文政13(1830)年に山口安良が記した『押原推移録』によると、現在の社殿が再建された慶長13(1608)年は日照りが続き人々の生活は困窮していた。
そこで神社別宮に集まって雨乞いをしたところ雨が降ったことから、人々は神徳に感謝し、雨のあがった6月19日に宵祭り、翌20日に例祭を行うこととした。その後、明治時代になって、例祭は秋となり、平成9(1997)年からは10月の第2土曜日と日曜日に実施するようになった。
華麗な装飾をした屋台が見どころ
この行事の見どころは、氏子各町内から曳き出される屋台である。なかでも毎年20基以上もの屋台が今宮神社に奉納される様子は実に壮観である。多くは周囲を豪華な彫刻で飾った四輪一層形式の囃子屋台で、全面に彩色が施されたものもある。
現存する最古の屋台の部材は、文化9(1812)年の石橋町屋台の欄間で、他にも日光五重塔彫物方棟梁後藤周二正秀、神山政五郎、現栃木市大平町富田の彫工礒辺一族など江戸時代後期を代表する彫師の名前が残る。これらは日光の宮大工の影響のもとに造られたと伝えられ、当時の技術力の高さはもちろん祭礼に対する市民の情熱を知ることができる。

受け継がれてきた祭りの運営
屋台の運行は、町内ごとに組織された若衆が仕切る。カナボウを先頭に町内を曳き回した後、あらかじめ決められた時間に、決められた場所を通って今宮神社の境内に繰り込む。そして、すべての屋台の繰り込みが終わり、神事が終了すると、それぞれの屋台を神社から繰り出して自分の町内に帰って行く。この頃になると屋台の提灯に火が灯り、幻想的な雰囲気となる。

お囃子を競い合う「ぶっつけ」
各町の屋台はお囃子を演奏しながら巡行する。「江戸ばか」「昇殿」「神田丸」「鎌倉」「四丁目」からなる五段囃子で、交差点などで複数の屋台が集まると「ぶっつけ」を行う。「ぶっつけ」は、2基以上の屋台が向かい合ってお囃子の競演を行うことである。相手のペースに飲まれずに、自分のリズムで演奏することを競うもので、沿道に集まった人々はその様子を見守る。囃子を担当するのは近郷の囃子連であるが、今宮神社の祭礼の囃子を務めることは誇りであった。

公開されている屋台は必見!
鹿沼今宮神社祭の屋台行事は本年も中止となり、屋台を曳き回す若衆や囃子連の勇姿を見ることができない。屋台だけでも見たいという方は、その一部が下記の施設で公開されているのでご覧いただきたい。
*臨時休館の場合がありますのでお出かけの際にはお問い合わせください
- 鹿沼市鹿沼市郷土資料展示室・・・鹿沼市睦町1956-2 TEL:0289-60-7890 屋台2基を展示(毎年入れ替え有)
- 屋台のまち中央公園・・・鹿沼市銀座1丁目1870-1 TEL:0289-60-6070 久保町、銀座1丁目、銀座2丁目の屋台を展示
- 木のふるさと伝統工芸館・・・鹿沼市麻苧町1556-1 TEL:0289-64-6131 石橋町の屋台を展示
- 仲町屋台展示収蔵庫・・・鹿沼市仲町1610-1 TEL:0289-62-1172(教育委員会事務局文化課文化財係)仲町の屋台を展示

1965年、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮大学大学院教育学研究科社会科教育専修修了。栃木県立足利商業高等学校、同喜連川高等学校の教諭を経て、1999年より栃木県立博物館勤務。民俗研究、とくに生活文化や祭り、芸能等を専門とし、企画展を担当。著書に『栃木民俗探訪』(下野新聞社)などがある。