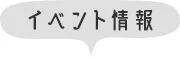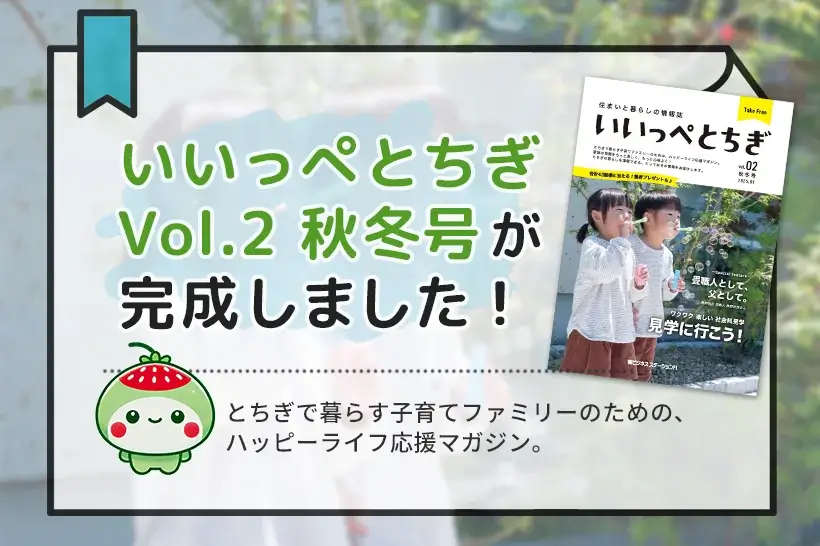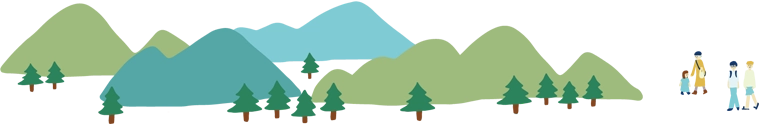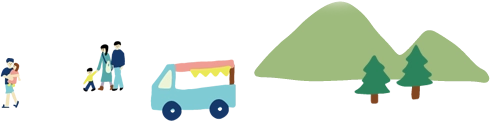人は誰しも、生を終える瞬間を迎えます。そのとき、栃木の人びとはどのように故人を見送り、どのように「あの世」と向き合ってきたのでしょうか。葬送のしきたりには、土地の歴史や信仰、そして人と人との結びつきが色濃く映し出されています。今回は栃木に伝わる葬送のかたちをたどります。
魂を呼び、旅立ちを見届ける
生きとし生けるものは、いつか死ぬ。葬式は、人生の最後に行う儀式である。それは、死亡したことを皆で確認し、故人をあの世へと支障なく送り出すための儀式でもある。

人が亡くなろうとする時、枕元でその人の名前を叫ぶ人は多い。民俗学ではこれをタマヨバイ(魂呼ばい)という。あの世へと旅立とうとしている霊魂を呼び戻すもので、なかには井戸の底にむかって、あるいは屋根にのぼって大声で叫ぶ人もいる。しかし、亡くなったと悟ると、死者に末期の水を飲ませ、北枕に寝かせてから胸の上には鉈や包丁、ハサミなどの刃物を置いた。
地域が支えた「ジャンボ」という葬式
「今日、葬式は葬祭業者が仕切ってくれる。しかし、昭和の終わり頃までは、葬式組などと呼ぶ近隣の人々からなる相互扶助で執り行われた。人が亡くなると施主は地域の代表(総代や班長)に連絡し、そこから葬式組に連絡が回る。連絡を受けると、すぐさま施主の家に集まり、葬式の日取りや役割を決めた。これには、葬式の采配をする帳場、亡くなったことを親類縁者に知らせるヒキャク、墓穴を掘るトコバンなどがある。そして、龍頭や花籠、枕飯、枕団子、死に装束など葬具類を準備した。
栃木県では、葬式はジャンボ、ジャーボ、ジャンボンなどという。僧侶がたたく饒(にょう)と鈸(ばち)の音がその由来とされる。読経をしてもらい、棺桶に蓋をすると出棺となる。昭和57年の芳賀町では、葬列は先松明を先頭に、龍頭、花籠、盛物、高張、幡、墓標、香炉、位牌、霊膳、前後の綱、天蓋、輿、輿添と続く。そして、その後を見送りの人々が付いて歩いた。墓地に到着するとトコバンが棺を土中に納めた。施主の家で清めを行い、念仏を行うと葬儀は終了するが、故人とのつながりは、その後も初七日、四十九日(本県では三十五日のことが多い)、盆、一回忌、三年忌など、少なくとも三十三年忌の弔い上げまで続く。

ケガレと向き合う、もうひとつの知恵
「ところで、死は人間にとって最大のケガレである。そのため、家族や地域にケガレが移らないように、日常とは真逆の作法がとられた。枕飯に箸を立てる、逆さ水(水に湯を足す)はその一例である。他にも死に装束を作る時は、鋏を使わず、糸に結び目はつけない、そして左前に着せるなどもある。
また、ケガレは火を通して伝染すると考えられたので、家の中で煮炊きすることを嫌った。なかには意味不明なしきたりもあるが、当時の人々が「死」や「あの世」といった得体の知れない物とどう向き合っていたのかがわかる。
人生の終焉に関する選択肢は増えてはいるが、家族や地域との絆が希薄となった現在、「死」に対する考え方は変化していくに違いない。
1965年、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮大学大学院教育学研究科社会科教育専修修了。栃木県立足利商業高等学校、同喜連川高等学校の教諭を経て、1999年より栃木県立博物館勤務。民俗研究、とくに生活文化や祭り、芸能等を専門とし、企画展を担当。著書に『栃木民俗探訪』(下野新聞社)などがある。