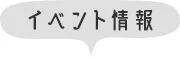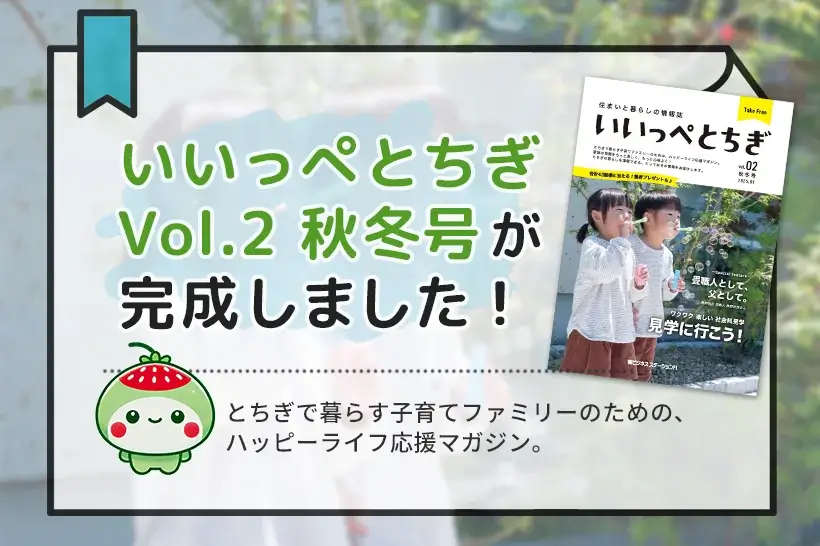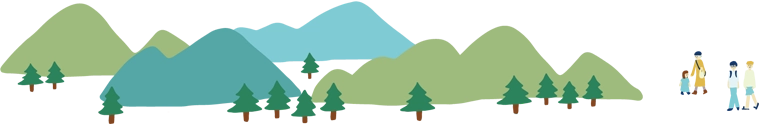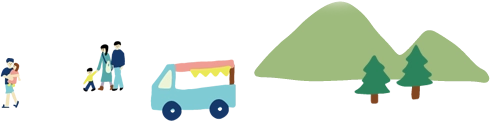宇都宮市出身。大学卒業後、食品メーカーに勤務。靴作りに興味をもち、靴の専門学校へ。2011年にUターンし2014年に独立。競輪場通り沿いで、靴修理店「amor」を営む。
https://www.facebook.com/kutushuritenamor4
宇都宮市競輪場通り沿いにある靴修理の専門店「amor(アモル)」。入口には古びた2足の革靴が。そして水色の扉の奥では、靴職人の田村侑子さんがていねいに何度も靴を磨いている姿がありました。
長く愛される靴づくり、その職人に憧れて
修理にいくらかかっても構わないからと、形見として譲り受けた靴を直しにくる人。高齢が理由で、これが最後の靴になるだろうと、メンテナンスを依頼する人。さまざまなストーリーがある靴が、所狭しと並ぶ店内。そのなかの1足を手にとって、お客さんとのエピソードを話してくれる田村さん。
「修理することがこんなに楽しいなんて、そこに気がつけて本当にラッキーだったんだと思います」
靴職人の田村さんが独立し、靴修理のお店を構えたのは2014年のこと。大学卒業後、食品メーカーに勤めていた田村さんですが、次第に「食べもののように、食べてしまったらなくなってしまうものではなく、いつまでも手元に残り続ける何かをこの手で作りたい…」と、思うように。自分で作った何かを扱う、自分のお店を持ちたい。ものづくりという職人業への憧れが強くなるうちに、大好きな靴への思いが募りはじめました。
「もともと靴は集めるのも履くのも好きだったんですけれども、これからのことをいろいろとネットで調べているうちに、製造工場で作られる靴以外にも、手仕事で靴を作れることを知ったんです。驚きだけでなく、何年も大切に履き続けられる靴を、私もこの手で作ってみたいと思いました」
挑戦するのは今しかない!
「23歳からならまだ間に合う!」 ある映画を観ていた時に偶然出会った、たった一言のこのセリフが、ずっと心に残っていたという田村さん。そのとき、まさに23歳。挑戦するなら今しかないと会社を退職し、浅草にある靴の専門学校へ進学を決意。2年かけて靴作りの技術を学びました。
そしていずれは作家として靴作りができたらと、独立を視野に入れ、まずは工房などへの就職を望んでいましたが、運悪く“リーマン・ショック”の影響を受け、求人はゼロ。それならとりあえずは靴の修理の職に就いて、落ち着いたらまた靴作りの仕事を探せばいいと、そんな気持ちで“作る”から“直す”へシフトチェンジしたのでした。
直すことで知り得る、靴に込められた“愛”のかたち
専門学校を卒業後、都内の靴修理店で働き始めた田村さんは、今まで思ってもみなかった、修理という世界の新たな魅力を知ることになります。
「それまで靴を直して履くという発想がなかったんです。本当に知らないことだらけですね(笑)。今頃になって後悔していますが、気に入った靴も傷んで履けなくなると捨ててしまったこともありました。だからこそ、それぞれに思いをもって、修理を希望されるお客さんの気持ちに寄り添いたいし、直してあげたいと思うんです」
お客さんとのやりとりが増えるごとに、靴を修理することへのやりがいを見いだした田村さんは、2011年に宇都宮市にUターン。資金の調達から物件探しなどの準備期間を経て、念願の独立へ向けて動きだします。そして2014年に今の店をオープンし、現在に至ります。
思いを捨てることがもったいない!
靴に込められた“愛”のかたち。その人にとって愛着のある靴を、これからも大切に履き続けられるようにすることが、靴の修理という仕事の魅力のひとつだと田村さんは話します。
「もともと日本人は『もったいない』という、日本にしかない言葉があるぐらい、本来ならば何も捨てられない人種だと思っているんです。それが時代の流れとともに、さまざまな場面で、日本特有の『もったいない』が、生活から離れていってしまったように感じます」
どんなに古くなったものでも、手入れをすれば使えるものもある。ものを捨てることがもったいないということではなく、そのものに込められた思いを捨てることが、もったいないことなのでは…。田村さんの言葉には、そんなメッセージがあるような気がしました。
一足の靴から生まれる喜び合い
「靴の修理には、いくつもの“喜び”があるんです。私自身が職人として靴を修理できる喜びと、お客さん自身が壊れた靴が直ったという喜び。そして、靴というものを大切にしあえる喜び。これって、ただただ幸せでしかない仕事ですよね」
新しいものを生み出すばかりではなく、今にあるものをこれからに伝える。そんな引き継ぎの文化を大切にしていく担い手となる田村さんも、立派な“つくり人”。
店名である「amor」は、ラテン語で「愛」を意味する言葉。つくり人の愛が込められ、新しく生まれ変わった靴は、この先、この靴の持ち主に幸せをもたらしてくれる、かけがえのないものとなるでしょう。