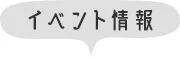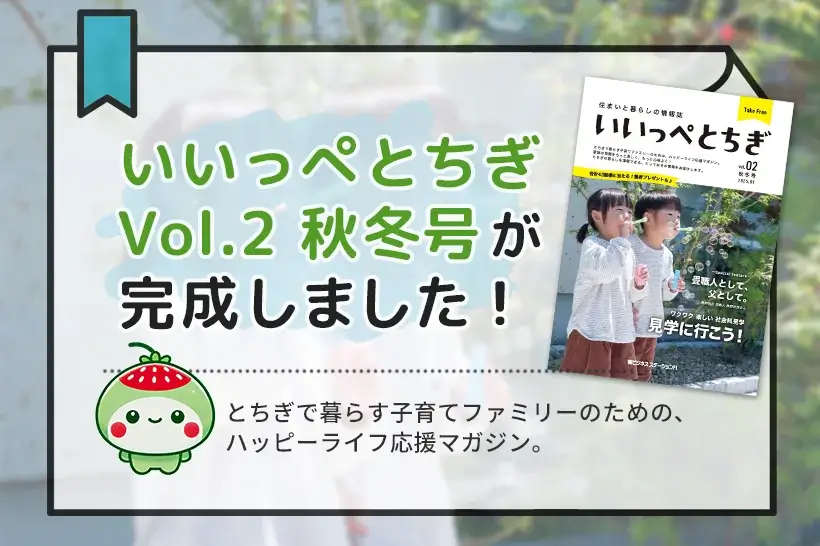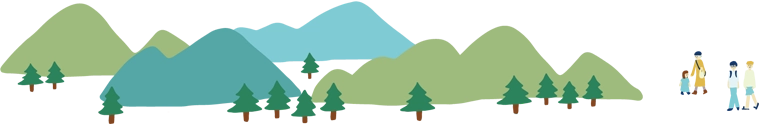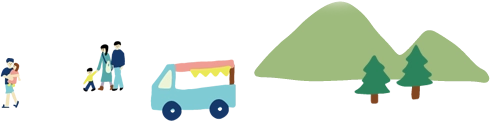縄文時代から利用されてきたタケの用具
タケの利用の歴史は、縄文時代にまでさかのぼることができ、ザルやカゴなどの生活用具や農具、漁具、信仰用具、調度品などさまざまなものが作られてきた。それは、タケが身近にあり、容易に利用できたからであろう。
明治時代から大正時代になると、技と創造性を高めることで、竹細工を芸術の域にまで高めた作家が現れた。栃木市出身の飯塚琅玕齋(いいづか・ろうかんさい1890-1958)もその一人である。琅玕齋の精神は、門弟である斎藤文石(さいとう・ぶんせき)に受け継がれ、大田原市出身八木沢啓造(やぎさわ・けいぞう)、勝城蒼鳳(かつしろ・そうほう)、藤沼昇(ふじぬま・のぼる)らに影響を与えた。彼らの作品は、世界中の人々から賞賛を受けている。
もっとも利用されているマダケとモウソウチク
今日、日本ではササを含め13属が生育しているが、もっとも利用されているのがマダケ属のマダケ(真竹)とモウソウチク(孟宗竹)である。他にササ属のチシマザサ(ネマガリダケともいう)、ヤダケ属のヤダケ、スズタケ属のスズタケ、メダケ属のメダケ(シノダケともいう)などもよく利用されている。
タケやササは稈(かん)、木本植物(もくほんしょくぶつ)でいうところの幹の内部が空洞になっているので、丈夫で軽く、しかも割裂性や弾力性、緊密性、柔軟性に富む。これらは種類によって異なり、生育地の環境によっても変化する。なかでも栃木県は、良質な材が採れる地域としても知られている。
マダケは、稈の表皮部が緻密で弾力性に富み、しかも節と節との間が長い。また割裂性が大きいので、編組製品の原料として好まれた。なかでも大田原市近辺は日本のマダケの北限に近く、身がよくしまった良質なタケが生育した。


粘りがあって曲げやすいシノダケ
栃木県の北部に位置する那須町高原地区では、ササの一種であるシノダケ(篠竹)を利用したざるかご作りが盛んである。寒冷地にある那須山麓では、付近に自生するシノダケを利用した笊籠作りが貴重な現金収入源であった。そこに暮らす人々は、子どもの頃から技術を習得し、農業の合間に製品を作った。シノダケは稈が細く、粘りがあって曲げやすい。厳しい自然で生育したシノダケからは、光沢があって、耐久性に優れた製品ができる。

ササや樹皮で作る美しいカゴバック
それよりさらに北に位置する福島県の会津地方では、チシマザサ、別名ネマガリダケと呼ぶササでザルやカゴを作る。これらの地域では、寒さと降雪のため良質なマダケは育たない。
さらに奥の山間部では、マタタビ、アケビ、ヤマブドウ、イタヤカエデなどで作られた生活用具に出会うことがある。そこには自然とともに生きる人々の姿を見ることができる。土地の風土や製作者の思いを想像しながら製品にふれてみるのもよいだろう。
1965年、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮大学大学院教育学研究科社会科教育専修修了。栃木県立足利商業高等学校、同喜連川高等学校の教諭を経て、1999年より栃木県立博物館勤務。民俗研究、とくに生活文化や祭り、芸能等を専門とし、企画展を担当。著書に『栃木民俗探訪』(下野新聞社)などがある。